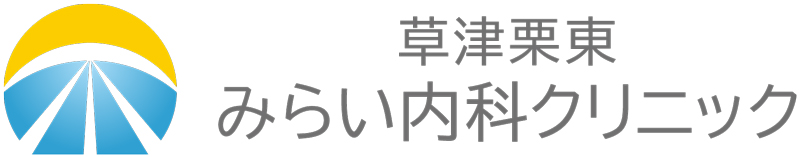重症喘息に対する生物学的製剤について
生物学的製剤(バイオ製剤)とは?
生物学的製剤は、特定の分子を標的として作用する抗体という物質を治療薬として使用する新しいタイプの薬剤です。
リウマチや膠原病などを中心に幅広い疾患で使用されていますが、最近では従来の治療ではコントロールできない重症の気管支喘息に対しても使われるようになっています。
生物学的製剤は、喘息の主な病態である「気道炎症」を引き起こす過剰な免疫反応を抑制することで効果を発揮します。
重症喘息とその問題とは?
吸入薬や抗アレルギー薬など既存の治療では、喘息の症状を十分にコントロールできない状態を重症喘息といいます。治療をしっかり継続していても、日常的に咳や痰、息切れや喘鳴(息の音がヒューヒューと鳴る)などの症状がとれない、風邪などをきっかけに頻繁に症状が悪化するような状態があてはまります。
このような状態ではしばしば経口ステロイド薬が必要になりますが、繰り返し内服したり少量でも長期間内服をつづけると、副作用が問題となります。
また、喘息は増悪を繰り返すことで、肺機能が低下していってしまうことが知られており、肺機能が低下することで、より喘息症状が強くなったり、さらに増悪を繰り返す悪循環に陥ってしまいます。
重症喘息に使用される生物学的製剤(バイオ製剤)は?
現在(2025年7月)、喘息にたいして使用可能な生物学的製剤は以下の5つです。
それぞれ、標的となる分子が異なり、患者さんそれぞれの喘息のタイプやアレルギーの特徴によってより効果の違いがあります。いずれも皮下注射で投与します。
治療薬の選択のためには、呼気一酸化窒素(FeNO検査)の結果や血液検査の結果(IgE、末梢血好酸球数など)、副鼻腔炎、アトピー性皮膚炎など併存する疾患の有無も参考にします。
・オマリズマブ(ゾレア®):抗IgE抗体
血液検査(RAST検査)で通年性吸入抗原に対するアレルギーが確認された方で、総IgE値が30~1500IU/mLの値の方が投与対象となります。IgE抗体を介したアレルギー反応を抑制します。2週間毎か4週間毎の投与となります。
・メポリズマブ(ヌーカラ®):抗IL-5抗体
IL-5を阻害することで好酸球を減少させることで効果を発揮します。好酸球が関与した喘息、特に血液中の好酸球数が多い方により効果が期待できます。4週間毎の投与となります。
・ベンラリズマブ(ファセンラ®):抗IL-5受容体α抗体
好酸球の活性化に関与するIL-5受容体α抗体をブロックすることでメポリズマブと同様に好酸球が関係している喘息に有効性が期待できます。初めの3回は4週間毎の投与で、4回目以降は8週ごとに投与します。
・デュピルマブ(デュピクセント®):抗IL-4受容体α抗体
IL-4やIL-13の受容体である抗IL-4/13受容体をブロックすることで気道上皮細胞や好酸球を介した免疫反応を抑制し効果を発揮します。喘息の他に、アトピー性皮膚炎や鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎等にも使用されています。初回は倍量を投与し、以後2週間毎に投与を行います。
・テゼペルマブ(テゼスパイア®):抗TSLP抗体
気道上皮細胞から分泌されるTSLPをブロックすることで、喘息症状の原因となる気道炎症を抑制します。他の製剤とは違い、2型炎症が亢進していない喘息にも効果が期待できます。4週間毎に投与します。
喘息に対する生物学的製剤のメリットとデメリットは?
これまでは、吸入薬などでコントロールが難しい喘息については、点滴または経口ステロイドを使用するしかありませんでしたが、特に頻回に使ったり、長期的に使用する場合には、副作用が問題となっていました。
生物学的製剤を使用することで、日常の症状が改善することはもちろん、季節の変わり目や風邪をひいたあとなどに症状が悪化する(喘息の増悪)を防ぐことで、全身ステロイドを投与する機会を減らせることは大きなメリットといえます。
喘息に対する生物学的製剤の副作用については、接種部位の腫れや痛みが時折みられます。また、まれな副作用としてアナフィラキシー反応などの可能性はありますが、問題となるような副作用は少なく、安全性の高い薬剤とされています。
デメリットとしては、薬剤が非常に高価であることです。製剤にもよりますが、薬剤費として、3割負担の方でおよそ3~5万円程度の自己負担になります。
負担を軽減する方法として、高額療養費制度や医療費控除を利用できる場合があります。また、健康保険組合によって独自の医療費助成がある場合がありますのでご確認ください。
当院での重症喘息の治療
開院から2年が過ぎ、当院にも多くの喘息患者さんに通院していただくようになりました。通常の治療でも症状コントロールが難しい重症喘息は全体の5~10%と言われていますが、当院でもやはり同様の割合でコントロールが難しい患者さんがおられると感じており、実際に生物学的製剤を使用される患者さんが増えてきております。
息苦しさや咳、痰などの症状が改善しない、特に増悪を繰り返して全身ステロイド(内服や点滴のステロイド)による治療が繰り返し必要になる場合には治療選択肢として生物学的製剤の治療を提示させていております。喘息の症状にお困りの方は、是非当院にご相談ください。
草津栗東みらい内科クリニック 院長 梅谷 俊介
・日本内科学会 総合内科専門医
・日本呼吸器学会 呼吸器専門医